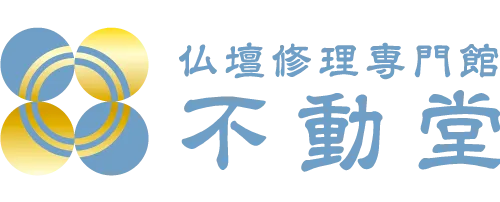(後半)初盆に必要な盆提灯とは?選び方・飾り方・マナーを徹底解説!
news
- お知らせ
- ブログ
こちらでは、前半「(前半)初盆に必要な盆提灯と準備の流れをご紹介」の続きとなります。
盆提灯サイズ・タイプの違いと選び方
盆提灯を選ぶ際に最も重要なのは、設置場所に適したサイズとタイプを選ぶことです。提灯のサイズは号数で表され、数字が大きいほど提灯も大きくなります。
提灯のサイズ分類
・大型提灯(12号〜15号)
- 高さ:約80cm〜120cm
- 適用場所:広い和室、仏間
- 特徴:存在感があり、格調高い雰囲気を演出
・中型提灯(9号〜11号)
- 高さ:約60cm〜80cm
- 適用場所:一般的な居間、仏壇前
特徴:バランスが良く、最も人気のあるサイズ
・小型提灯(6号〜8号)
- 高さ:約40cm〜60cm
- 適用場所:マンション、コンパクトな仏壇
特徴:省スペースで現代的な住環境に適応
・ミニ提灯(3号〜5号)
- 高さ:約20cm〜40cm
- 適用場所:デスクトップ、小さな仏壇
- 特徴:場所を選ばず設置可能
タイプ別の特徴
置き提灯
最も一般的なタイプで、台座があり床や台の上に置いて使用します。
安定性が高く、移動も比較的容易です。初心者にはおすすめのタイプです。
吊り提灯
天井や専用の吊り具から下げて使用するタイプです。
空間を立体的に使用でき、より幻想的な雰囲気を演出できます。
行灯型(あんどんがた)
四角い枠に紙を張った伝統的な形状の提灯です。安定感があり、和室によく合います。絵柄も美しく描かれているものが多く、芸術性も高いです。
マンションなど省スペース向け提灯とは
現代の住環境では、従来の大型提灯を設置することが困難な場合が多くあります。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、限られたスペースを有効活用できる提灯の選択が重要です。
省スペース提灯の特徴
コンパクトサイズ 省スペース向け提灯は、通常6号(約40cm)以下のサイズで設計されています。これにより、狭いリビングや小さな仏壇の前でも無理なく設置できます。
壁掛けタイプ
床面積を使用せず、壁に掛けて使用するタイプの提灯です。専用の金具を使用して壁に固定し、高さのある場所からの照明効果を得られます。
テーブルトップタイプ
ダイニングテーブルやサイドテーブルの上に置ける、極小サイズの提灯です。高さ20cm以下のものが多く、普段の生活の邪魔になりません。
LED電源タイプ
電池式やUSB電源のLED提灯は、電源コードが不要で設置場所を選びません。また、熱を発生しないため、小さな子供がいる家庭でも安心して使用できます。
省スペース提灯の選び方のポイント
設置予定場所の寸法測定:購入前に必ず設置場所の幅、奥行き、高さを測定してください。
周囲の家具との調和:現代的な家具との調和を考え、デザインを選択してください。
安全性の確保:狭いスペースでは特に、転倒防止や火災対策を重視してください。
収納のしやすさ:お盆期間外の収納も考慮し、分解・組み立てが容易なものを選んでください。
盆提灯の飾る時期とタイミング
盆提灯を飾る時期は、地域の慣習や宗派によって若干の違いがありますが、
一般的なタイミングをご紹介します。
【一般的な飾り付けスケジュール】
7月お盆の地域(東京など)
- 7月1日〜7月6日:提灯の準備・設置
- 7月7日:七夕、提灯の点灯開始(地域により異なる)
- 7月13日:お盆入り、迎え火
- 7月16日:お盆明け、送り火
8月お盆の地域(その他多くの地域)
- 8月1日〜8月7日:提灯の準備・設置
- 8月7日〜8月12日:提灯の点灯開始
- 8月13日:お盆入り、迎え火
- 8月16日:お盆明け、送り火
詳細なタイミング
設置のタイミング 提灯の設置は、お盆入りの1週間前から前日までに行うのが一般的です。初盆の場合は特に丁寧に準備したいため、早めの設置をおすすめします。設置後は、電気系統の動作確認や安全点検も忘れずに行ってください。
点灯開始のタイミング
提灯への点灯は、地域により異なりますが、多くの場合お盆入りの日の夕方から開始します。迎え火を焚くのと同時、またはその直後に提灯に灯りを灯すのが一般的です。
点灯時間
お盆期間中は、夕方から夜中まで点灯させるのが基本です。ただし、安全性を考慮し、就寝時には消灯しても構いません。電気式の提灯の場合は、一晩中点灯させることも可能です。
片付けのタイミング
お盆明けの送り火の後、翌日から翌々日にかけて提灯を片付けます。白提灯は通常この時に処分し、絵柄提灯は来年のために大切に保管します。
設置場所と配置の基本
盆提灯の設置場所と配置は、故人の霊を迎え入れるという神聖な目的を果たすため、適切に行う必要があります。
基本的な設置場所
仏壇前 最も一般的な設置場所は仏壇の前です。仏壇を中心として、左右対称に提灯を配置するのが基本です。仏壇が東向きや南向きの場合は、その前の適切な距離を保って設置します。
精霊棚(しょうりょうだな)周辺
精霊棚を設ける場合は、その周辺に提灯を配置します。精霊棚は故人の霊が滞在する特別な場所とされるため、提灯の配置も特に丁寧に行います。玄関付近 門提灯や迎え提灯として、玄関やアプローチに設置することもあります。これは故人の霊が迷わず家に辿り着けるよう、道標の役割を果たします。
配置の基本ルール
対称性を重視する 提灯を複数設置する場合は、左右対称の配置を心がけます。これは調和と安定を表現し、故人の霊が安らげる環境を作るためです。
適切な間隔を保つ 提灯同士の間隔は、提灯の大きさの1.5倍から2倍程度を目安とします。あまり近すぎると圧迫感があり、離れすぎると一体感が失われます。
高さを揃える 複数の提灯を設置する場合は、高さを揃えることで統一感を演出します。台座の高さを調整するなどして、提灯の中心部分の高さを合わせてください。
動線を考慮する 日常生活の動線を妨げない位置に設置します。特に小さな子供がいる家庭では、安全性を最優先に考えて配置してください。
【設置時の注意点】
・安全性の確保
- 不安定な場所への設置は避ける
- 燃えやすいものから十分な距離を保つ
- 小さな子供の手の届かない高さに設置
・風水的配慮
- 北向きや鬼門方向への設置は避ける傾向
- 清浄な場所への設置を心がける
- 直射日光が当たる場所は避ける
灯りを灯す時間帯やマナー
盆提灯の点灯には、適切な時間帯とマナーがあります。これらを守ることで、より意味のある供養を行うことができます。
点灯時間の基本
日中の点灯 昼間は基本的に消灯しているのが一般的です。ただし、初盆や特別な法要の際には、日中でも点灯することがあります。
夕方からの点灯
日が傾き始める夕方5時頃から点灯を開始します。これは故人の霊が活動を始める時間とされているためです。
夜間の点灯
夜中まで点灯させるのが理想的ですが、安全性や近隣への配慮から、就寝時には消灯しても構いません。電気式提灯の場合は、一晩中点灯させることも可能です。
朝の消灯
朝6時から7時頃に消灯します。これは故人の霊が休息に入る時間とされているためです。
点灯時のマナー
点灯前の準備 点灯前には、必ず手を洗い、心を清めてから行います。
また、提灯の状態を確認し、安全に点灯できるかどうかをチェックします。
点灯の仕方
点灯は丁寧にゆっくりと行います。急いで点灯するのではなく、故人への思いを込めながら、一つずつ順番に灯していきます。点灯中の注意 点灯中は、提灯の周りを清潔に保ち、お供え物を整えるなど、故人への供養を心がけます。
消灯時のマナー
消灯時も点灯時と同様に、丁寧に行います。故人への感謝の気持ちを込めて、一つずつ消灯していきます。
特別な日の点灯
迎え火の日 お盆入りの日は、迎え火と同時に提灯に灯りを灯します。
送り火の日
お盆明けの日は、送り火と共に提灯の灯りも最後に灯します。故人の霊をお見送りする意味を込めて行います。
法要の日
僧侶による読経や法要が行われる日は、その間中点灯を続けます。
誰が盆提灯を用意するの?
家族?親族?贈るべき人・贈られる側のマナー
盆提灯を誰が用意するかについては、地域の慣習や家族の関係性によって異なりますが、一般的なルールとマナーをご紹介します。
基本的な用意者
白提灯 白提灯は通常、故人の家族(配偶者や子供)が用意します。これは初盆の特別性を示すものであり、故人に最も近い関係者が準備するのが適切とされています。
絵柄提灯 絵柄提灯は、親族や友人、知人から贈られることが多いです。故人への思いを込めた贈り物として、また供養に参加する意思表示として贈られます。
地域別の慣習
・関東地方
- 家族が白提灯を用意
- 親族が絵柄提灯を贈答
- 兄弟姉妹からの贈り物が重視される傾向
・関西地方
- 家族・親族が協力して用意
- 地域コミュニティからの贈り物も重要
- より幅広い関係者が関与する傾向
・九州地方
- 家族が中心となって用意
- 親族の結束が重視される
- 贈答提灯の格式が重要視される傾向
贈る側のマナー
贈るタイミング 提灯は、お盆の2週間前から1週間前までに贈るのが一般的です。あまり早すぎても遅すぎても、先方に迷惑をかける可能性があります。贈る相手の確認 同じような提灯が重複しないよう、事前に他の親族や知人と相談することが大切です。不動堂でも盆提灯を準備しております。

まとめ
初盆は、故人を偲び心を込めて迎える大切な行事です。その象徴となる盆提灯を選ぶことで、より丁寧な供養の場を整えることができます。飾り方や選び方、贈る際のマナーなどをしっかり押さえて、安心して準備を進めましょう。不動堂では、お電話1本でお客様がご希望する盆提灯のご用意できますので、ぜひご連絡お待ちしております!!